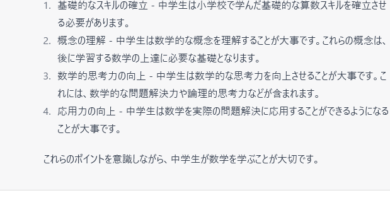理科の学習成果を上げる(1)
理科の学習成果を上げる
どの科目にも言えることですが、
理科という科目・学習に興味を持つことがスタートです。
興味がないことには学習意欲がわきません。また、現状の理解力を大幅に超えたことには意欲どころか拒否反応が起こってしまいます。好きなことは、自ら情報収集するので自然と詳しくなっていきますが、逆のケースでは、まったく情報を持っていないため、ある事柄を説明されてもチンプンカンプンなんてことにも、、、。
ですから、普段から身の回りの出来事にちょっとずつでも興味をもって見ているかどうかが大きく影響します。
周りの出来事に興味を持つかどうかは、周囲の環境や友人関係、家庭の状況等が大きいと思います。
虫好きの父親なら、子供はムシに抵抗感はなくなりますが、ゴキブリに異常な嫌悪感を表す家庭で育てば
虫全般がきらいになっていくようです(ペットショップでは大型のゴキブリの仲間も販売していますが、まぁ、ゴキブリが好きな方はごく少数だと思います)。
お母さんが花好きでいろいろ育てていれば、子どもは植物に目が行くようになります。季節ごとに咲く花の違いにも目が行くようになります。
育つ家庭環境はとっても大事な条件となります。


ここの教室では、多くの生き物を飼育しています。昆虫(カブト、クワガタ、キリギリス、鈴虫他)両生類(ウーパールーパー、イモリ)、爬虫類(やもり)、魚類(メダカ)、甲殻類(エビ)、植物(エノキ、ウマノスズクサ、ヘンルーダ、山椒、イチゴ、レタス他)


普段目にすることで、自然に親しみもわき関連した知識が学習で出てきた時 全く知らないではなく、覚えるときの知識の土壌となります。
ここの通ってくる子たちは理科の好きな子が多いし、ますます好きになっていくのは僕のひいき目かな(^^♪
中学生になると覚えないといけないことが格段に増えてきます。色んな語呂合わせを作ってまずは知識のインプットができるように準備しています。
夏季や冬季の季節講習時には物理や化学の実験を一緒に行ったりすることもあります。事前準備で結果を予想し、実験後には結果の考察を通して知識を深めてもらいます。(実験したことは忘れにくいですね。体を動かし、あれこれやるので記憶に残りやすくなります。)

理科は実験が楽しい!とほとんどの子が答えます。
ただ、学校でも塾でも限られた時間ではあれもこれもやれないのでほとんどのことは図で説明して終わってしまいます。残念なことですが、仕方ありませんね。
AIに注目が集まり、IT人材育成が声高に叫ばれる時代、理系人材になる第1歩が理科好きから始まると思います。好奇心、探求心の豊かな子どもになり、将来の日本を背負って立てるような人材に育てていきましょう。